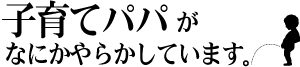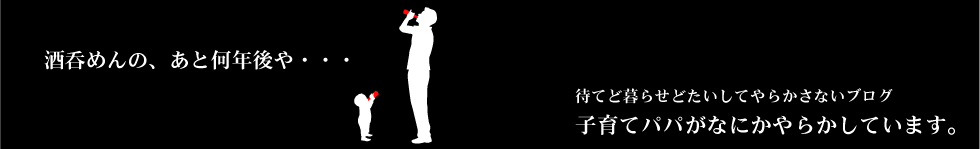子供の体や病気の相談は何科に行けばいいの? 我が家はこうしてるよ
2015/02/27

子どもが生まれるまで、子どもがこんなに熱を出すもんだなんて知りませんでした。
親としてもそれなりに準備をしておかないと、突発的な子どもの病気やケガに対処できない。オロオロするだけで何の役に立たないオヤジは、知らぬ間に下がっている家庭内での評価がぶざまにもっと下がるだけです。
ママ任せではなく、パパも準備しておかないとね。
夜中に高熱を出して病院に駆け込んだり、玄関から転げ落ちてたんこぶ作ったり、ドアに足を挟んで爪はがれたり、椅子から落ちて鎖骨骨折したり、他にも何があったか忘れちゃったくらいだけど、3歳の息子も妻も僕もだいたい一通り(?)こなして耐性が出来てまいりました。
親も子も時間に鍛えられ、経験でなんとかなっていくものかもしれませんが、最初はやはりいろいろ不安。
「子どもの病気やケガはそもそも何科に行けばいいの?」
「子どもの体や成長について不安な場合、どこに相談すればいいの?」
「夜間や休日に病院に行くべきかどうか悩んだらどうすればいいの?」
子どもの体や病気の相談をしたい場合に我が家がどういう基準で動いているのか? 緊急時に備えてどう準備しているのか?を今回は偉そうに書いてみます。
スポンサーリンク
子どもの体の相談先はどこか?
「小児科」が基本

何でも「小児科」でOK
「あたりまえだろ」とツッコミが聞こえてきそうですが、僕は我が子が生まれたての頃、「なにかあったらとりあえず小児科に行けばいい」という基本さえ知らなかった。世のパパなんて、みんなそんなもんじゃないのかな。
基本中の基本「子どもの身体に関する相談ごとは「小児科」に軸足を置くべし」
何かあればまず「小児科」に行って指示を仰ぐ。
骨が折れてるかも?など、素人でも明らかに判断がつけば「整形外科」直行でいいですし、親も経験を積むと「何科にいけばいいか?」の判断がつくようになりますが、わからない場合はとりあえず「小児科」です。極論、擦り傷でも何でも全部「小児科」行き。
小児科で手に負えなければ、専門の科に行ってこいと言われます。うちの息子は今までに小児科経由で「耳鼻科」「眼科」「皮膚科」「肛門科」に飛ばされました。
信頼できる医者は、きちんとした医者を紹介してくれます。適当なところを紹介して対応がまずかった場合、紹介した側の信用問題にモロに直結するため、「◯◯科ならどこに行けばいいですか?」と同業者に質問をぶつける作戦はかなり効果的。下手に自分で探して変な医者に当たるより、断然いい。
小児科医との信頼関係が大切
「おすすめの医者は?」といったぶしつけな質問に答えてもらえるよう、常日頃、小児科との先生との信頼関係を築いておくことが大切です。
予防接種などで定期的に先生と顔を合わせるので、僕も妻も時間が許されるのであればその際などに気になっていることをちょろっと聞いたりしてます。僕は仕事が休みの時に息子の診察の付き添いを買って出たりと、何かあった時のために美人小児科医の元に足繁く通っております。
「普段の生活で気になること」「発達で気になること」「アレルギー」などもバンバン聞いてます。先日は診察がすいてたので「幼児にマスクって意味あるんですか?」と聞いてみた。
関連記事 子供にマスクは何歳から大丈夫?そもそも効果はあるのか?
うちの子の食物アレルギーがわかったのも、先生との会話からでした。肌が弱いため「いつもの湿疹だろう」と、診療終わりのついでに「最近こんなものが」と先生に相談。
「一度、血液検査してみましょうか」 そこから返ってきたアレルギー陽性の結果に、夫婦して仰天したという・・・
親子に合う小児科を探す

住んでいる環境にもよります。周囲に小児科やこどもクリニックがたくさんあれば比較検討できるけど、あんまり選択肢がない場合もあるかと。
どんな環境にせよ、小児科に限らず、子どもの様子を経過観察してくれる近場の内科などかかりつけ医はきちんとひとつ決めておいたほうが良いです。「遠くの名医より近くのお医者さん」発想ですね。
待ち時間や予約方法などのシステム面や、話をきちんと聞いてくれる先生か、我が子と親の病院へのフィーリングもあるでしょう。
小児科によっては、他の科にかからずともすぐに関連の薬を出してくれる、強い薬を出してくれる、傾向がさまざまです。
信頼のおけるクリニックを効率的に探す方法は「ない」。周囲の評判などを聞きつつ、地道に探す以外ないのかなと思います。
「自治体サービス」も活用
住んでいる自治体の保健所や保健センター、子育て支援センターなどでも子どもの体についての疑問を相談できます。子どもの日常生活や成長などで気にかかることへの質問に、積極的に答えてくれる。
自治体の定期健診の時に、子どもの発達についての心配事を相談してもいい。
小児科では対応しきれない「親としての子育ての不安」なども自治体はフォローしてくれます。親への精神的なサポートなども。
直接会って話をする以外に、電話相談窓口も準備されていたりします。どこの自治体も、ホームページに細かく「こういうサービスやってます」と書いてありますので、一度チェックしてみるといいかと思います。
緊急時はどこに相談するのか?

何をもって「緊急」とするかは悩ましいところですが、我が子のことを一番知っている親が「緊急だ」と思ったら緊急なのかも。
これはマズいと直感したら、躊躇せずに救急車を呼ぶべきです。
とはいえ、救急車の搬送は半数が入院を必要としない「軽症」とのこと。消防庁が「子どもがこういう時は救急車を呼ぶべし」と、判断基準になる「救急車利用マニュアル」を出しているので一読しておくといいかもしれません。
参考 消防庁「救急車利用マニュアル」
それでも「これは緊急なの?緊急じゃないの?」「病院行くべきなのだろうか?」と我が子のことを思うばかり、やきもきすることは多い。そういう時はネットで検索もいいですが、専門相談窓口にすぐに電話してみるのが得策です。
親が知っておくべき救急電話相談3つの窓口と、おすすめサイトをまとめておきます。
国運営「小児救急電話相談」
小児救急電話相談事業(#8000)について|厚生労働省
国が運営している「小児救急電話相談事業」の電話窓口があります。
「#8000」をコールすると各都道府県の救急電話相談窓口へ転送され、医師や看護師が電話口に出る。症状を聞いた上で受診の可否をジャッジしてくれます。病院へ行く必要がある場合は、近くの救急病院の連絡先を教えてくれる。
夜間や休日に起きた子どもの急な病気やケガは、ここに電話して相談すれば、親が一晩悶々とすることはなくなりそうです。
都道府県ごとに受付時間が違うので注意。あとIP電話と光電話からは#8000が使えないため、直通電話番号へ。下のリンクに詳細が書いてあります。
参考 厚生労働省「小児救急電話相談事業(#8000)について」
自治体運営「救急相談」
県単位、市区町村単位と、それぞれの自治体が「小児救急電話相談窓口」を開設しています。県の場合は上記「小児救急電話相談」の転送先。あとは市区町村で独自に運営する窓口があるパターンもあり、市民限定の健康相談窓口と兼用だったりも。
相談の時間は「夜間のみ」「24時間」と自治体によりまちまち。
「地名+救急相談」でネット検索をかけるとすぐに番号が出てくるので、住んでいる自治体でどのような緊急時の電話窓口が存在するのか、どの程度まで相談に乗ってくれるのか、受付日と受付時間はチェックしておいたほうがいいです。
消防庁運営「救急相談センター」
東京消防庁<救急相談センター>
消防庁が「救急相談センター」「救急安心センター」を開設しているので、いちおう押さえておきましょう。
こちらは残念ながら地域限定サービス。現在は、東京や大阪、奈良、愛知などが対象。
「#7119」にコールすると、症状を聞いた上で、電話口で緊急性があるかどうかのアドバイスをしてくれます。24時間365日対応。
#8000同様、IP電話と光電話からは通じないため直通電話番号へ。
参考 東京消防庁「救急相談センター」
サイト「こどもの救急」
子どもの健康について調べることができるサイトは世にごまんとありますが、運営元が「日本小児科学会」できちんとしており、使い勝手も良い「こどもの救急」というサイトをおすすめしておきます。
対象年齢は生後1ヶ月~6歳まで。
こどもの救急
このサイトの設立目的は「小児救急医療受診者は9割以上が軽症の患者であり、中には受診しなくても大丈夫だった患者もいる。現場は疲弊しており、小児救急医療受診者を減少させたい」とのこと。
なかなかよく出来ているサイトです。スマホ対応もしてます。僕があれこれ説明するより、ぜひ一度見てみてください。
子どもの症状をポチポチと入力して結果を見ると、「救急車で病院に行く」「病院に行く」「家で様子見」などの指示が出てきます。医師へ親が「症状を伝える際のポイント」や、家で様子見の場合の「看病ポイント」はかなり参考になるはずです。
参考 こどもの救急
まとめ

「通常時の備え」と「夜間休日時の備え」と「緊急時の備え」
常日頃からパターンを考えて備えておくことで、突発的に起こる子どもの病気やケガにも素早く対応できます。僕は「妻がいなくて自分ひとりのときに息子に何か起きた場合、どうしたらいいのか?」を考えて、上記の準備をしています。
かかりつけの小児科への行き方がわからないんじゃ困るのでほいほいついていく。先生とちょこちょこ会話して顔見知りになっておく。「電話が混んでいて通じないがな!」という時のために複数の救急相談窓口を調べておく。サイトも使いこなしておけば出先で役立つかもしれない。
いつ起こるかわからぬものに対して、不安を煽っているわけではありません。ただ、何か起きてから慌てて対応策を調べ出すのでは遅い。だからすぐに動けるように準備をしておく。時間をかけて小児科医との信頼関係を築いておく。
自分の準備不足が自らの身に振りかかるだけなら自業自得ですが、我が子にまで影響は及ぼしたくないのはその親にも共通する想い。「備えあれば憂いなし」ですよね。
ことわざでブログの最後を締めるとかおっさんくさいな。
ad
ad
関連記事
-

-
子どものひとり自転車は親の前と後ろどちらを走らせるのが良いのか?検証してみる
祝。我が子が自転車一人乗りで公道デビューをしました。 はて? 親の自転車と子ども …
-

-
初耳!東海道新幹線「のぞみ」に家族向け専用車両がある?
子連れ新幹線でお困りの方は多いようで、当ブログの人気記事になっている2本の記事。 …
-

-
「足の爪の正しい切り方」をご存知ですか?私は30年以上間違ってました
息子との爪切りタイムは至福の時間 なぜか息子(2歳)の爪は私がずっと切ってます。 …
-

-
子供の写真をフォトプロップスの無料素材を使って撮ると超楽しいよ
「フォトプロップス」を使用して写真撮影をすると、けっこう楽しめる。 フォトプロッ …
-

-
子供の誤飲事故はどういうパターンが多いのか?厚生労働省の報告から学ぶ
あたりまえだけど、我が子は親が守らないと。 普段のほほんと暮らしていると「そんな …
-

-
パンパースのすくすくギフトポイントって3年でどれくらい貯まるの?
パンパースのおむつとその周辺商品には、「すくすくギフトポイントプログラム」という …
-

-
子供連れ「すみだ水族館」事前準備ガイド。スカイツリーの下の水族館に行く前の予習ができます。
東京スカイツリーの麓にある「すみだ水族館(隅田水族館)」 水族館はだいたい海に面 …
-

-
出産祝いのプレゼントにおすすめ!メッセージカードも兼ねた「アマゾンギフト券」
出産祝いに「アマゾンギフト券はないだろ」という保守的意見も否定はしない。 「プレ …
-

-
なぜ自動改札の扉はベビーカーや幼児が通っても閉まらないのか?
駅の自動改札をベビーカーで通るのが苦手です。 通路幅に対してベビーカー幅は余裕あ …
-

-
今人気のおもちゃって何だろう?「日本おもちゃ大賞2014」からおさらいしてみよう
こんなショーをやっているのを初めて知りました。「東京おもちゃショー2014」 東 …